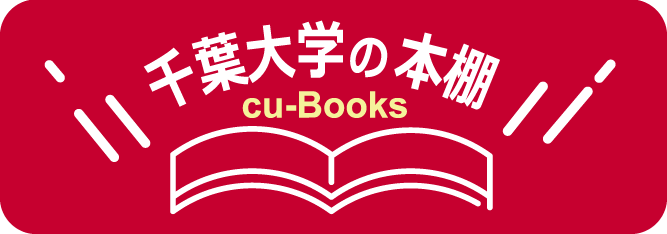お知らせ
Stay at home and keep learning! 千葉大学の新入生,そして在校生の皆さんへ
更新日: 2020-4-17 対象:全館
4月はキャンパスが最も華やぐ時期です。大学生活に目を輝かせている新入生,学年が一つ上がり気持ちも新たに勉学に励む在校生でキャンパスは満ちあふれます。附属図書館/アカデミック・リンク・センターでも,新入生のためのガイダンス,アカデミック・リンク・ウイークなど新学期の行事が目白押しで,留学ガイダンスには,あふれんばかりの学生さんが図書館1階のプレゼンテーションスペースに集まる…はずだったのですが,新型コロナウイルス感染症の流行にかかる緊急事態宣言,それに伴う入構規制によりキャンパスは静かな4月を迎えています。
この静かな時間を無為に過ごしてほしくないと思い,皆さんに読んでほしい本のリストを作成しました。このリストに含まれるのは,アカデミック・リンク・センターが開催している「1210あかりんアワー」という学生向きのランチタイムセミナーで先生方にご自身の研究についてお話しいただいた際に,お話に関連する本として推薦があったものです。その中でも,電子書籍として本学が購入し,キャンパス外からアクセスできるものに限定しました。もしかしたら日頃の関心とは異なる分野の本の方が多いかもしれませんが,中身を覗いてみて面白そうだなと思ったらぜひしっかりと読んでください。また,「1210あかりんアワー」での先生方のお話は,一部のみですが学内者限定で動画配信もしています。ネットワーク環境を考慮して,それぞれ無理のない範囲で読んだり視聴したりしてください。
また徳久剛史学長の「リーダーたちの本棚」(朝日新聞2017年3月25日掲載)も併せてご紹介します。図書館が自由に利用できるようになったらぜひこれらの本も手にとってみてください。オンラインで本を読むのが厳しいという皆さんには,お手元にある過去に読んだ本を読み返してみることをお勧めします。不思議なことに,何度読んでも新しい発見のある本というのはあるものです。そのような本こそが,皆さんにとっての古典,すなわち時を超えて読み継ぐべきものだと思います。
現下の危機的な状況にあっても学生の皆さんには学びの楽しさ,素晴らしさを忘れてほしくない,また,この時間を有効に使ってほしい。附属図書館/アカデミック・リンク・センターは,そのような思いで様々な電子的サービスを提供し続けていきます。詳細については「オンライン学習支援ポータル」(スマートフォン対応),「自宅からでも利用できる電子コンテンツ」を参照してください。
みなさんとキャンパスでお目にかかる日がすぐにくることを期待しつつ。
2020年4月
千葉大学附属図書館長
アカデミック・リンク・センター長
竹内 比呂也
「1210 あかりんアワー」教員が研究の楽しさを語る 推薦図書:【あかりんBOOKS】
新入生,そして在校生の皆さんに読んでいただきたい本をリストアップしました。
アカデミック・リンク・センターが開催しているランチタイムセミナー「1210あかりんアワー」の
<教員が研究の楽しさを語る>シリーズで,先生方にご自身の研究についてお話しいただいた際,関連する本として推薦いただいたものです。その中でも電子書籍として本学が購入し,キャンパス外からもアクセスできるものに限定して掲載しています。
※学外からの電子ブックの利用方法については,以下をご覧ください。
新入生の皆さんは,大学から利用者番号などのご案内が届いたら利用できます。
Maruzen eBook Library 学外からの利用方法
EBSCO eBook Collection 学外からの利用方法
Japan Knowledge ジャパンナレッジLib 学外からの利用方法
※リストは今後も順次追加していきます。(2020.7.13更新)
人文社会科学分野
| 推薦教員(敬称略) (登壇時所属) 登壇回(日時) |
書名 (電子ブックにリンクしています) |
推薦コメント |
|---|---|---|
| 宮寺千恵 (教育学部) 第238回(2019.11.19) |
ソーシャル・マジョリティ研究 : コミュニケーション学の共同創造 (コ・プロダクション) 綾屋紗月編著 ; 澤田唯人 [ほか] 著 金子書房, 2018.11 |
神経発達症,その中でも特に自閉スペクトラム症の多くの方は,コミュニケーションがとても苦手であると言われています。コミュニケーションが苦手,といっても,コミュニケーションとは何か?が定義されないとコミュニケーションについて考えることは困難です。この本では,日常の中で何気なく行っている会話,人との関わりについて,それが苦手な人の視点から捉えなおすことができる本だと思います。 |
| 川久保友超 (社会科学研究院) 第237回(2019.11.12) |
Small area estimation 2nd edNEW J. N. K. Rao and Isabel Molina John Wiley & Sons, 2015.8 |
小地域推定の分野をリードし続けてきた研究者による著書です。小地域推定に用いられる統計手法の理論と,官庁統計をはじめとする応用例がまとめられています。 |
| 皆川宏之 (社会科学研究院) 第229回(2019.7.16) |
「同一労働同一賃金」のすべて 水町勇一郎著 有斐閣, 2018.2 |
2018年に成立した働き方改革関連法では,「同一労働同一賃金」に関する法改正が目玉の1つとなりました。本書では,日本版「同一労働同一賃金」の実現を提唱し,雇用形態における労働条件格差是正のための立法にあたって大きな役割を果たした著者が,今回の法改正に至る経緯と新しい規制の内容について解説しています。 |
| 石井雄隆 (教育学部) 第225回(2019.6.18) |
語学学習支援のための言語処理(自然言語処理シリーズ 11) 永田亮著M コロナ社, 2017.11 |
言語をコンピュータ上で扱う自然言語処理という研究領域から言語教育にアプローチした書籍。ライティング学習支援や言語能力の自動評価などを扱っている。 |
| ガイタニディス ヤニス (国際教養学部) 第215回(2019.1.29) |
Consuming religionNEW Kathryn Lofton The University of Chicago Press, 2017.9 |
現代社会は完全な消費社会であるという表現があります。この本は現代社会でみられる消費行動(ドラマの一気見や金融グループのゴールドマン・サックスの考え方など)を宗教研究を通して、実は理解可能な行動であると議論しています。「宗教」とはまったく関係がないと思ったところの解説まで「宗教」という概念が役に立つと教えてくれる一冊です。 |
| 岸本信 (社会科学研究院) 第213回(2019.1.15) |
産業組織とビジネスの経済学 花薗誠著 有斐閣, 2018.9 |
生産・販売などに関して企業が戦略的に行う意思決定を,ゲーム理論を応用して分析した本です。企業にとって最適な経営戦略の分析という観点だけでなく,政府の立場からも社会全体にとって望ましい経済政策について議論しています。理論的な知見だけでなく,現実例との関連も解説しています。 |
| 見城悌治 (国際教養学部) 第208回(2018.11.27) |
満洲国留日学生の日中関係史 : 満洲事変・日中戦争から戦後民間外交へ 浜口裕子著 勁草書房, 2015.10 |
戦中期に「満州国留学生」として日本で学んでいた2名に焦点を当て,聞き取りも交え,当時の状況をリアルに復元している。この2名が戦後は,日中友好に尽くす役割を果たす事に,歴史の数奇さを感じることができる。 |
| 留学生は近代日本で何を学んだのか : 医薬・園芸・デザイン・師範 見城悌治著 日本経済評論社, 2018.3 |
千葉大学のルーツにあたる戦前期の諸学校で,医学薬学,園芸,デザイン,師範教育を受けていた留学生の在学中の修学状況,帰国後の活動に全貌について詳細にまとめた著作。日本社会との交流や軋轢も明らかにした。 | |
| 帝都東京を中国革命で歩く 譚璐美著 白水社, 2016.8 |
明治末期の中国留学生が多く住んでいた「神田」「本郷」「早稲田」の古地図を示し,どこでどのような活動をしていたのか,分かりやすく説明する。カラー写真,現在との対比も多く,都市の変化も知ることができる。 | |
| 佐野晋平 (社会科学研究院) 第196回(2018.7.3) |
幼児教育の経済学 ジェームズ・J・ヘックマン著 ; 古草秀子訳 東洋経済新報社, 2015.7 |
ノーベル経済学賞受賞者であるヘックマンの貧困対策に関する講演をまとめた本です。「不利な家庭環境の子ども対する介入は効率性・公平性を同時に達成する政策手段だ」という政策提言を著者の研究成果をベースに簡潔に説明されています。 |
| 砂上史子 (教育学部) 第185回(2018.4.17) |
ノーベル経済学賞を受賞したヘックマンによる幼児教育の投資効果に関する研究知見を,分かりやすく解説しています。その知見は,国際的にも広く認知され,非認知的能力の重要性や保育の質の向上など,日本を含めた各国の政策に影響を与えています。個人の人生を生涯にわたって支えるのみならず,効率性と公平性を両立する社会政策としても注目されている幼児教育の意義を知ることができます。 | |
| 阿部明典 (人文科学研究院) 第189回(2018.5.15) |
チャンス発見の情報技術 : ポストデータマイニング時代の意思決定支援 大澤幸生監修・著 東京電機大学出版局, 2003.9 |
チャンス発見の初期の本 |
| Chance DiscoveryNEW Lakhmi C. Jain, Yukio Ohsawa, and Peter McBurney Springer, 2003.1 |
||
| 一人称研究のすすめ : 知能研究の新しい潮流 諏訪正樹, 堀浩一編著 ; 伊藤毅志 [ほか] 共著 近代科学社, 2015.4 |
一人称研究という客観主義とは相対した学問の提案 | |
| Philosophy and Cognitive Science : Western and Eastern StudiesNEW Lorenzo Magnani and Ping Li Springer, 2012.7 |
認知科学と哲学の論文集 | |
| Computational and Cognitive Approaches to NarratologyNEW Takashi Ogata and Taisuke Akimoto Information Science Reference, 2016.7 |
物語の自動生成などの論考 | |
| Content Generation Through Narrative Communication and SimulationNEW Takashi Ogata and Shin Asakawa Information Science Reference, 2018.2 |
||
| 高橋信良 (国際教養学部) 第183回(2018.1.30) |
演劇の歴史(文庫クセジュ, 923) アラン・ヴィアラ著 ; 高橋信良訳 白水社, 2008.4 |
西洋演劇はどのように変遷していったのか。フランス演劇の歴史を中心に解説した本です。演劇を知るうえで押さえておくべき基本概念をコンパクトにまとめた本書は,「演ずるとは何か」を考えるための恰好の入門書です。 |
| 佐伯 昌彦 (社会科学研究院) 第175回(2017.11.21) |
犯罪被害者の司法参加と量刑 佐伯昌彦著 東京大学出版会, 2016.4 |
犯罪被害者が刑事裁判に参加することによって量刑に影響は生じるか。生じるとすると,その影響はどのような性質のものであろうか。本書では,刑事裁判における犯罪被害者の関与の在り方を考えるうえで参照されるべき実証的な知見の提供を目指した研究の成果を紹介しています。 |
| 法と社会科学をつなぐ 飯田高著 有斐閣, 2016.2 |
本書では,社会科学の最先端の知見を平易に解説し,そのような社会科学の知見から法学の問題をとらえ直しています。扱うトピックは細かく分かれており,一つの項目ごとに簡潔にまとめられているので,気になるトピックを選んで読み進めていくこともできます。 | |
| 佐藤宗子 (教育学部) 第167回(2017.7.25) |
現代児童文学を問い続けて(児童文学批評の新地平 1) 古田足日著 くろしお出版, 2011.11 |
「現代児童文学」出発期から評論と創作の双方で中心的な役割を果たし続けてきた著者による,最後の評論集。歴史的な概観と,21世紀の状況へのまなざしがわかる。 |
| 「物語」のゆらぎ : 見切れない時代の児童文学(児童文学批評の新地平 3) 奥山恵著 くろしお出版, 2011.11 |
1990年代からゼロ年代にかけて,世界全体が変化する中で,児童文学の<物語>をどう捉えるかという問題に迫る。本書で著者は日本児童文学者協会新人賞を受賞。 | |
| 牛谷智一 (人文科学研究院) 第166回(2017.7.18) |
発達(心理学研究法 4) 山口真美, 金沢創編著 誠信書房, 2011.8 |
発達心理学の方法を解説した本ですが,最後は動物の知覚を調べる方法について私が執筆した章があります。 |
| 米村千代 (人文科学研究院) 第153回(2017.4.18) |
秩序と規範 : 「国家」のなりたち(岩波講座日本の思想 第6巻) 苅部直 [ほか] 編集委員 岩波書店, 2013.6 |
「イエの変遷」という章を執筆しています。近世から現代までの「家」の変遷を思想史という視点からまとめています。 |
| 岡田聡志 (高等教育研究機構) 第138回(2016.10.18) |
大学の条件 : 大衆化と市場化の経済分析 矢野眞和著 東京大学出版会, 2015.12 |
学び習慣仮説の提唱とその実証を通じて,大学で学習することの意義についてアプローチしています。 |
| 白川優治 (国際教養学部) 第128回(2016.6.7) |
大学進学の機会均等化が,社会的にも経済的にも合理的であること,つまり,それが社会全体のためになることを実証的に示しています。矢野眞和『「習慣病」になったニッポンの大学―18歳主義・卒業主義・親負担主義からの解放』(日本図書センター,2011年)とも合わせて手にとってもらいたいと思います。 |
理工学分野
| 推薦教員(敬称略) (登壇時所属) 登壇回(日時) |
書名 (電子ブックにリンクしています) |
推薦コメント |
|---|---|---|
| 綿野泰行 (理学研究院) 第235回(2019.10.29) |
森の分子生態学 : 遺伝子が語る森林のすがた(種生物学研究 第23号) 種生物学会編 文一総合出版, 2001.2 |
第一部の第5章で,今回話題提供するハイマツとキタゴヨウの種間交雑の話が載っています。今となっては古い本ですが,DNAなどの分子情報を使った進化研究の入門書として今でもお勧めできます。 |
| 花輪 知幸 (先進科学センター) 第219回(2019.5.7) |
人類の住む宇宙 第2版(シリーズ現代の天文学 1) 岡村定矩 [ほか] 編 日本評論社, 2017. |
私たちの住む宇宙はどのようにして生まれてきたのか。また宇宙についての私たちの理解はどのようにして形成されてきたのかについて書かれています。日本天文学会が一般読者向けにまとめたもので,著者・編者ともに優れた方々で,読みやバランスよく書かれています。今回のお話で取り上げる星・惑星形成は第4章で紹介されています。 |
| 松本洋介 (理学研究院) 第216回(2019.4.9) |
深層学習 = Deep learning(MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 岡谷貴之著 講談社, 2015.4 |
ディープラーニングを始める上で,この2冊の本を読んで勉強しました。前者は理論中心,後者はpythonを使ったプログラミング例が記載されているのが特徴です。誤差逆伝搬法は後者の計算グラフを使った説明がわかりやすかったので,両書を併せて読むのをおすすめします。 |
| ゼロから作るdeep learning : Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装※ 斎藤康毅著 オライリー・ジャパン , オーム社 (発売), 2016.9 |
||
| 安田 賢司 (理学研究院) 第212回(2019.1.8) |
Mechanism of functional expression of the molecular machines(Springer briefs in molecular science )NEW Masahiro Kinoshita Springer, c2016. |
タンパク質の様々な振る舞いには水のエントロピーが重要な役割を果たしています。本書では特にATP駆動タンパク質に関して、その機能発現のメカニズムを水のエントロピーに注目して解析した結果を、他の教科書とは異なる独自の観点でまとめています。 |
| 下村義弘 (工学研究院) 第204回(2018.10.30) |
商品開発・評価のための生理計測とデータ解析ノウハウ―生理指標の特徴,測り方,実験計画,データの解釈・評価方法 三宅 晋司 (監修) ; 日本人間工学会PIE研究部会 (編集) エヌティーエス, 2017.3 |
脳波や筋電図などの生体情報の測定から利用方法までがわかりやすく紹介されています。 |
| 泉賢太郎 (教育学部) 第194回(2018.6.19) |
生痕化石からわかる古生物のリアルな生きざま 泉賢太郎著 ベレ出版 (発行・発売), 2017.10 |
生痕化石とは,生物の行動の痕跡が地層中に保存されたもので,“生物の行動の化石”と言えます。恐竜図鑑をはじめ,化石に関する本や図鑑はたくさんありますが,本書は生痕化石を題材として書かれた数少ない本のひとつです。本書では,生痕化石の実例を写真やイラストともに紹介することで,古生物の生態にスポットライトを当てています。さらに,日ごろは垣間見ることが少ない,専門研究の現場の様子についても紹介されています。地層や化石について事前知識がない方でも気軽に読んでいただけるように意識して執筆しました。 |
| 土松隆志 (理学研究院) 第181回(2018.1.16) |
植物はなぜ自家受精をするのか(シリーズ・遺伝子から探る生物進化 5) 土松隆志著 慶応義塾大学出版会, 2017.8 |
植物の生殖をテーマに進化生物学の研究に取り組んだ,私自身の研究半生記です.大学生から大学院,海外での研究員時代などの研究の過程をまとめています。ちょうど大学生くらいの方に読みやすい本になっていると思います。 |
| 伊藤彰一 (医学研究院) 第146回(2016.12.13) |
理系のための研究生活ガイド : テーマの選び方から留学の手続きまで第2版(ブルーバックス, B-1671) 坪田一男著 講談社, 2010.2 |
眼科臨床医である著者が,研究テーマの決め方から留学の手続きまで,わかりやすい言葉で情熱をもって語ります。 |
| 坂本一之 (融合科学研究科) 第141回(2016.11.8) |
表面物性(現代表面科学シリーズ 3) 日本表面科学会編 ; 坂本一之担当編集幹事 共立出版, 2012.10 |
固体表面で発現する様々な新奇物理現象,化学現象を理解するための入門的な本である。 |
※「ゼロから作るdeep learning : Pythonで学ぶディープラーニングの理論と実装」は電子書籍化されていませんが,「深層学習 = Deep learning」とセットでご推薦いただいたので掲載しました。紙の本は所蔵していますので,図書館が利用できるようになったらぜひ手に取ってみてください。
医学・薬学・看護分野
| 推薦教員(敬称略) (登壇時所属) 登壇回(日時) |
書名 (電子ブックにリンクしています) |
推薦コメント |
|---|---|---|
| 安西 尚彦 (医学研究院) 第245回(2020.1.21) |
栄養・食品機能とトランスポーター 竹谷豊 [ほか] 責任編集 建帛社, 2011.5 |
動植物の種類を問わず,細胞の恒常性の維持,成長や増殖にとって必要な栄養素は,細胞膜を通過して細胞内に取り込まれて働くことができる。その細胞膜の物質の透過に関与するのが膜タンパク質の一つのトランスポーターである。本書は主要な栄養素の細胞膜トランスポーターについて書かれた入門的なものである。 |
| 中村浩之 (薬学研究院) 第239回(2019.11.26) |
脂質解析ハンドブック : 脂質分子の正しい理解と取扱い・データ取得の技術(実験医学別冊) 新井洋由, 清水孝雄, 横山信治編集 羊土社, 2019.10 |
「私,この分野の専門外ですけど,脂質解析をやってみます!」という初心者から,脂質解析を日頃行っている経験者まで,脂質の基本的な性質をゼロから学び,間違いのない取り扱いが行えるようになる実験バイブル。 |
| セラミド研究の新展開 : 基礎から応用へ セラミド研究会編集 食品化学新聞社, 2019.6 |
国内のセラミド研究者の総力を結集して,その基礎から幅広い応用研究を網羅した参考書。 | |
| 伊藤晃成 (薬学研究院) 第230回(2019.7.23) |
もっとよくわかる!免疫学(実験医学 別冊) 河本宏著 出版:羊土社, 2011.2 |
分かり易い説明とユニークな漫画絵(著者が描いてる),知的好奇心を刺激する考察が随所にあり,楽しく読み進むことができます。免疫学の初心者はもちろん,ある程度知識を持った方にもお薦めできる一冊です。 |
| 浦尾悠子 (子どものこころの発達教育研究センター) 第223回(2019.6.4) |
自分で治す「社交不安症」 :自分に自信が持てる!! 清水栄司著 法研, 2014.12 |
人に接したり,人前に出ることに強い不安を感じてしまう社交不安症は,若い人を中心に多くの人が悩んでいます。症状がひどくなると,学業や仕事に支障が出たり,不登校やひきこもり状態になる人もいます。この本は,社交不安をもつ方が,自分で本を読みながら,認知行動療法のメソッドを活用して不安を解消していくための具体的な方法が紹介されています。 |
| 山本修一 (附属病院長) 第200回(2018.10.2) |
ロービジョンケアの実際(専門医のための眼科診療クオリファイ, 26) 山本修一編 中山書店, 2015.2版 (発行・発売), 2017.10 |
有効な治療法のない網膜変性患者のQOL改善に欠かせないロービジョンケアを臨床現場でサポートします。 |
後藤義幸 (真菌医学研究センター) 第164回(2017.7.4) |
ヒトマイクロバイオーム研究最前線 : 常在菌の解析技術から生態,医療分野,食品への応用研究まで 服部正平監修 NTS, 2016.3 |
最新の研究成果をまとめた「腸内細菌の教科書」として貴重です。腸内細菌の解析法や機能,応用まで幅広くカバーしており,腸内細菌の研究を志す人には大変興味深い内容になっています。 |
| 織田成人 (医学研究院) 第158回(2017.5.23) |
医療スタッフのためのやさしく解説!日本版敗血症診療ガイドライン 織田成人監修 学研メディカル秀潤社 , 学研マーケティング (発売), 2013.12 |
2012年11月に発表された「日本版敗血症診療ガイドライン」を,医師以外のメディカルスタッフにもわかりやすく解説した書籍です。 多臓器不全の第一位の原因である敗血症は早期の診断・治療を必要とします。講演者の織田は,日本集中治療医学会のSepsis Registry委員会の委員長として,本ガイドラインの策定において中心的役割を果たしました。 本ガイドラインはこのたび改訂され,「日本版敗血症診療ガイドライン2016」として,2017年2月に発表されました。 |
| Hemoperfusion, Plasmaperfusion and Other Clinical Uses of General, Biospecific, Immuno and Leucocyte AdsorbentsNEW Thomas Ming Swi Chang, Yoshihiro Endo, and Volodymyr G. Nikolaev World Scientific, 2017.4 |
血液中から吸着の原理を用いて、様々な物質や血球を分離・除去する技術と、その臨床応用に関する研究成果を集めた書籍です。2017年3月に発刊されました。編者の一人、Dr. Changは、血液吸着の第一人者です。講演者の織田は、長年研究・開発に携わってきたPMMA(ポリメチルメタクリレート)膜ヘモフィルターを用いた持続的血液濾過透析(CHDF)に関する項を執筆しています。 |
園芸学分野
| 推薦教員(敬称略) (登壇時所属) 登壇回(日時) |
書名 (電子ブックにリンクしています) |
推薦コメント |
|---|---|---|
| 矢野佑樹 (園芸学研究科) 第217回(2019.4.16) |
人工光型植物工場 : 世界に広がる日本の農業革命 古在豊樹著 オーム社, 2012.3 |
近年世界的に注目を集めいている人工光を利用した植物工場の基礎知識・用語が体系的にまとめられています。 |
| 人文・社会科学のためのテキストマイニング(改訂新版) 松村真宏, 三浦麻子著 誠信書房, 2014.9 |
フリーソフトウェアを組む合わせることで,無料でかつ本格的にテキストマイニングを行うための方法が紹介されている本です。応用事例も紹介されており,テキストマイニングの奥深さや面白さを知ることができると思います。 | |
| 野村昌史 (園芸学研究科) 第172回(2017.10.31) |
観察する目が変わる昆虫学入門 野村昌史著 ベレ出版, 2013.6 |
昆虫とは,に始まり昆虫の生活や生態,そして昆虫観察するときのアドバイスなど多岐にわたる内容ですが,写真もたくさん掲載しているので,気楽な昆虫学の教科書にもなりますし,読み物としても読みやすい本です。 |
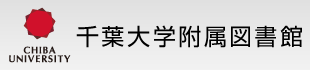 千葉大学附属図書館
千葉大学附属図書館