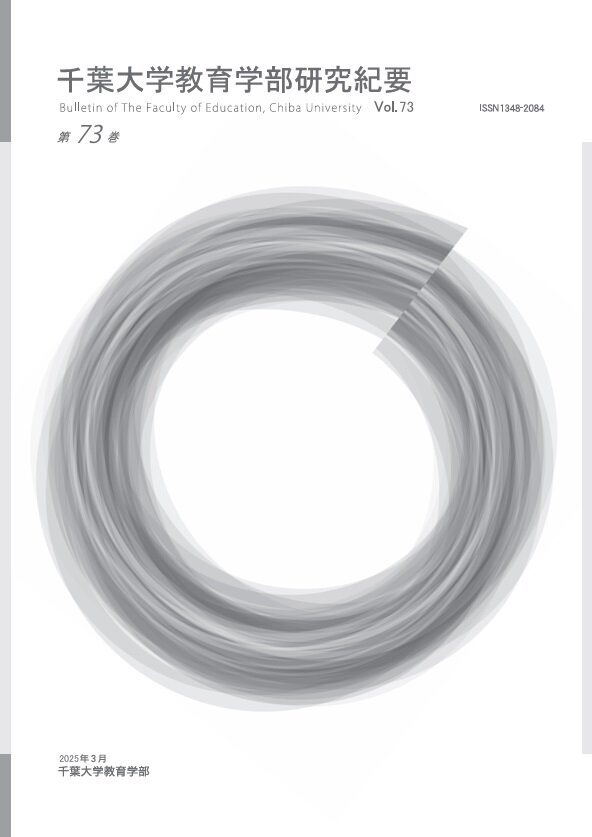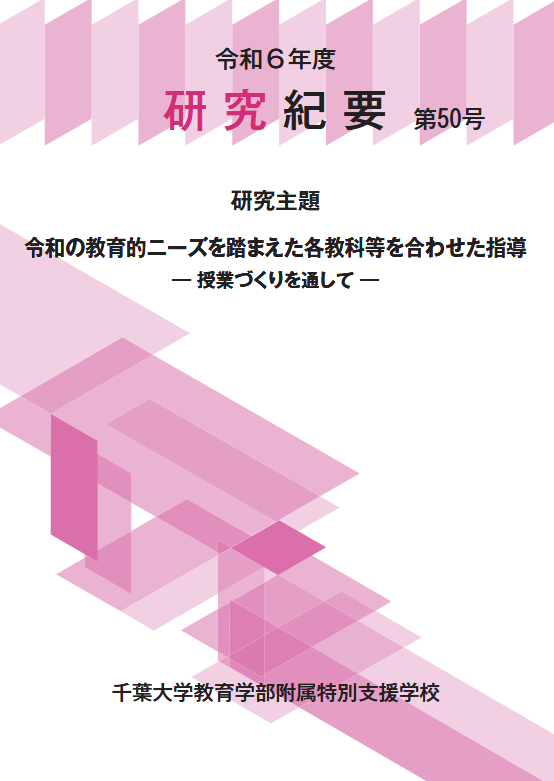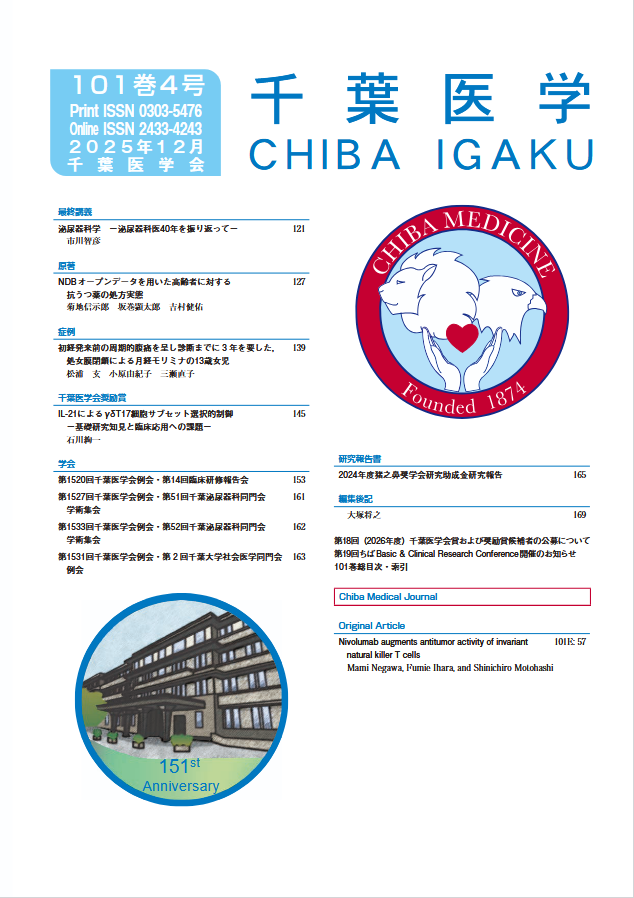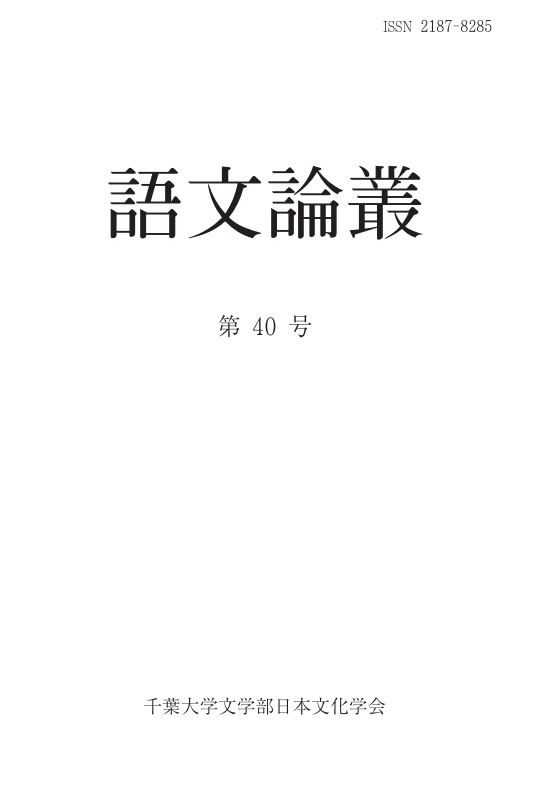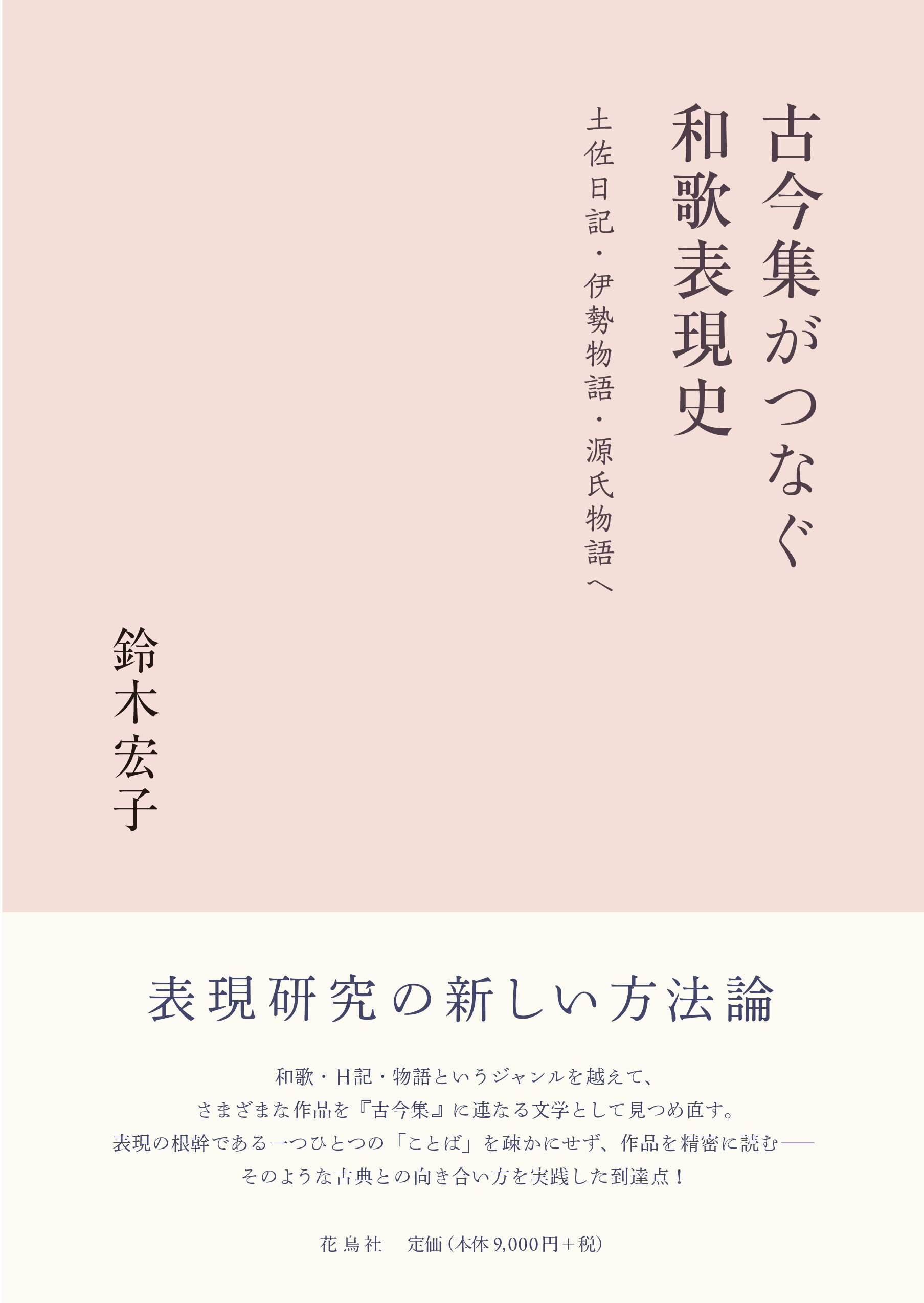目次
Ⅰ.教育科学系
● 障害疑いのある児童保護者への支援に関する一考察 ~養護教諭による支援とアウトリーチの点から~
佐々木 千絵・石田 祥代
● 1人1台端末を活用した自立活動の指導に関する一考察
古川 幸夫・石田 祥代
● 特別支援学校における知的障害児のICT利活用の実際と個別の利用状況
木下 武治・新妻 翔太郎・石田 祥代
● 科学的リテラシーを育む「千葉大学×墨田区」プロジェクト:小学校6年「水溶液の性質」の支援例
林田 優・山下 修一・古市 綾乃
● 科学的リテラシーを育む「千葉大学×墨田区」プロジェクト:小学校6年「植物の養分と水の通り道」の支援例
松下 伊織・山下 修一・保刈 栄紀・池田 莉都
● 科学的リテラシーを育む「千葉大学×墨田区」プロジェクト:ソメイヨシノの生殖方法に関する読み物教材開発と評価
畑﨑 江美・山下 修一・保刈 栄紀・及川 美幸
● 小学校4年「空気と水の性質」における質的・実体的な見方を育む理科授業
松下 伊織・山下 修一
● 小学校5年「物の溶け方」における個別探究のための問題解決シートの開発と評価
葭葉 彩子・山下 修一
● 教員のメンタルヘルスの現状と分析
笠井 孝久
● 科学技術振興機構グローバルサイエンスキャンパスの支援による千葉大学ASCENTプログラムのSTEAM教育としての4年間の成果
野村 純・Peter Nkachukwu CHUKWURAH・Jose Said GUTIERREZ-ORTEGA・眞鍋 佳嗣・秋本 行治・飯塚 正明・牛谷 智一・大西 好宣・古谷 勝則・松元 亮治
● 保健室DXの現状調査(1) ~学校で収集する健康情報のデジタル化の現状
杉坂 くるみ・高谷 里依子・土屋 綾子・森重 比奈・野村 純
● 保健室DXの現状調査(2) ~学校で収集する健康情報をデジタル化するメリットとデメリット~
杉坂 くるみ・高谷 里依子・土屋 綾子・森重 比奈・野村 純
● 中学生の鉱物と岩石における認識
土屋 貴嗣・丸澤 和晃・三野 弘文
● 教育学部保健体育科専攻学生のICT活用指導力の実態とその育成 ―個人種目におけるICTの活用に着目して―
下永田 修二・小泉 岳央
● 1960年代における小泉文夫のわらべうた研究と音楽教育実践との関わり ―園部三郎・羽仁協子・日教組との関わりを中心に―
本多 佐保美
● 教員養成課程の学生を対象とした生成AIリテラシー・ワークショップの開発と評価
齋木 匠・石井 雄隆
● 小学校でのものつくりの教育における「改良」に関わる教材開発
鈴木 隆司
● 保育者養成課程における表現教育の在り方の検討 ―表現科目担当者を対象としたグループ・インタビューを通して―
駒 久美子
● 大学生と現職保育者からなる多層・交流型「リトミック・ワークショップ」の意義 ―参加者の認識の変化と効果の分析―
鈴木 香代子・駒 久美子・砂上 史子・中道 圭人
● 国立研究開発法人科学技術振興機構の次世代科学技術チャレンジの支援による千葉大学ASCENT-6Eの開発
野村 純・王 茜・森重 比奈・眞鍋 佳嗣・秋本 行治・飯塚 正明・牛谷 智一・大西 好宣・片桐 大輔・高木 啓・古谷 勝則・松元 亮治・小澤 弘明
● 高等学校家庭科における家族学習の変遷 ―「家族機能」に着目した教科書分析を通して―
福田 楓・中山 節子
● 学校や学校設置者によるいじめ対応のゲーム的構造
藤川 大祐
● 酪農教育ファームの活動・課題・展望についての実態調査 ―関東地方の認証牧場を対象に―
音田 和泉・辻 耕治
● 中学1年生のスピーキング・タスクに見る誤りからの一考察
物井 尚子・佐藤 玲子・尼寺 圭悟・渡部 尚美
● 千葉県公立高校入試英語リーディング分野と中学校英語教科書の語彙分析 ―語彙の重なりの観点から―
若松 千智・星野 由子
● 病気の子供の支援について重要視する内容に関する検討 ―X県の病弱教育に関わる教員と小・中学校等の通常学級の教員を対象とした質問紙調査―
原田 友里・宮寺 千恵
● 教育における身体と学びの関わり ―教育における身体の捉え直し―
杉山 英人
● 中国におけるリハビリテーション訓練教育課程に対する教師の認識 ―肢体不自由教育に着目して―
金 業格・椎 寿美・任 龍在
● 若手教師の授業に関する資質・能力を対象とした研究の現状と課題
遠藤 みなみ・八木澤 史子・佐藤 和紀・堀田 龍也
● 統計的探究プロセスにおける多様な考えを生かす算数科教材研究 ―データの「よいところ」を多様に捉え結論付ける活動に着目して―
梶原 太志・辻山 洋介
● 統計的問題解決の授業における児童の批判的考察の過程 ―問題の文脈を自分事として捉えることに着目して―
柴田 政之・辻山 洋介
● 小学校における優秀児や気になる児の行動特徴 ―Renzulli et al.(2010)に基づいた予備的検討―
中道 圭人・髙橋 実里
● 幼児における「場所の占有」に関する理解の発達
林 冬実・中道 圭人
● 青年の社会的自己効力感は主観的幸福感に寄与するのか?:3つの社会的関係に着目して
髙橋 実里・小川 翔大・中道 圭人
● インクルーシブ保育での仲間との遊びにおける情動共有 ―接面の生成と変容を手がかりに―
細川 かおり
● 知的障害者のためのものづくりワークショップの教育実践
木下 龍・佐藤 守・深井 もも・程 麗君・山口 理生・角 綾乃
● スポーツメンタルトレーニング的側面から考える保健体育授業について ―ボール運動(ネット型)への応用に向けて―
西野 明
● 低年齢児保育の質及び質評価に関する国際的な動向と展望
淀川 裕美・箕輪 潤子・峰 友紗・堀 科・猪熊 弘子・菅井 洋子・今福 理博
● 教員養成課程の教育実習生における給食の残食に対する考え方 ―大学生活での給食指導の学びの有無の視点から―
川嶋 愛・大貫 友莉・崎谷 彩花・中西 明美・鈴木 隆司
● スウェーデンにおける幼児期数学教育の現状 ―観察とインタビューを通して―
松尾 七重
● 外国につながる児童支援の教員研修 ―担当教員のインタビューを通して―
中西 啓介・本田 勝久
● 名詞句把握から文を読むことへとつなげる指導 ―小学校での外国語科(英語)と国語科の連携の試み―
田中 真理・西垣知佳子・橋本 修・安部 朋世・神谷 昇
● 小学生が自身と重ねて史資料を読み解く歴史学習単元開発研究 ―「大人と子どもの境界」に着目して―
戸田 善治・小関悠一郞・木口恵理子・仁平 夏実・松島 広輔・由井薗 健・石原 鉄也・岩野 敬・上澤 塁志・齋藤 圭介・富松真二郎・継田 朋之・山本 慧一
● 海外での授業実践を通じた特別支援学校教員の意識 ―グローバル教員育成研修に向けて―
細川 かおり・任 龍在・金 容漢
● 日本人および中国人学習者に対して出版された小学校英語教科書における社会形態とアイデンティティの交差分析
本田 勝久・長谷川 喜大・閆 雨彤
● 応急手当の学習に関する大学の教員養成カリキュラムの現状
榎本 朔美・野村 純
● 保護観察中の成人男性の再犯リスク及び保護観察官・保護司の接触頻度と再犯との関連
羽間 京子・勝田 聡
● 発達支援に関わる情報に保護者はどのようにアクセスしているのか ―自治体からの情報提供とSNSを含めたソーシャルメディアに注目したアンケート調査―
真鍋 健・明田 楓可・森 菜津子
● 中学校におけるL2文法学習の効率の最適化:ペーパー版DDLとペーパー+ウェブベースDDL
西垣 知佳子・尼寺 圭吾・中井 康平・川名 隆之・見目 慎一・山崎 達也
Ⅱ.人文・社会科学系
● 児童の非言語行動の表出と教師のかかわり合いに関する検討 ―小学校第2学年の「体つくりの運動遊び」を対象にして―
七澤 朱音・秋田 喜代美
● ストレス関連の過食行動に影響を与える要因についての検討
花澤 寿
● サブサハラ・アフリカにおける食糧供給・食糧消費の全体像とその変遷,1962-2019 ――産出エネルギーによるアプローチ――
妹尾 裕彦
● 「教科における探究的な授業」のつくり方
小山 義徳
● 専門職業としての里親はいかにして可能になったか ―パリ市および近郊の里親へのインタビューをもとに―
安藤 藍
Ⅲ.自然科学系
● 藍と黄色系天然染料の交染による緑系染色布の色彩と光退色(第2報) 長期曝露による緑系染色布の光退色挙動
谷田貝 麻美子
● 電圧の概念を取り入れた電気教材の検討
飯塚 正明・我妻 沙紀
● 窪田浅五郎の考案した路程車の復元と機能および精度の検証(第二報:路程車の構造分析,設計と図面化および作業工程計画の立案)
吉野 葵・桂本 柚奈・板倉 嘉哉
Ⅳ.芸術系
● 造形素材としての砂の可能性の探究:教員研修を通して
小橋 暁子・槇 英子・井上 郁
● 中学校美術科における文化遺産としての伝統工芸のカリキュラム ―デザイン活動に着目して―
佐藤 真帆
学部・研究科等
キーワード
新着記事
-
-
-
-
-
-
-
-
Cooperative evangelist : Kagawa Toyohiko and his world, 1888-1960
著者:Bo Tao
出版社:University of Hawaiʻi Press
出版年:2025年
-
-